食物アレルギー ~当科での取り組みについて~
小児科│主任部長 鎌田研治医師
食物アレルギーとの出会いは40年ほど遡ります。小学六年生になると一年生の給食配膳のお手伝いに行くのですが、担当したクラスで一人だけ配膳しなくて良いと言われた子がいました。ほかの子と違っている様子もないのですが、その子は毎日お弁当を持ってきていました。当時の私は偏食が強く給食が苦手(担任の先生が厳しくお残し禁止)だったものですから、「羨ましいなぁ」と言う気持ちしかありませんでした。
そのようなタイミングでたまたまテレビのニュースで、食物アレルギーのためパンや白飯が食べられない小学生が毎日お芋のお弁当を持って登校しているという映像を見て、「あの子と同じだ!」となったわけです。当時すでにアレルギー性鼻炎を発症していた私でしたが、アレルギーのために食べ物が食べられない人を目の当たりにして、「アレルギーとは・・・?」と気になる存在になりました。
そのようなタイミングでたまたまテレビのニュースで、食物アレルギーのためパンや白飯が食べられない小学生が毎日お芋のお弁当を持って登校しているという映像を見て、「あの子と同じだ!」となったわけです。当時すでにアレルギー性鼻炎を発症していた私でしたが、アレルギーのために食べ物が食べられない人を目の当たりにして、「アレルギーとは・・・?」と気になる存在になりました。
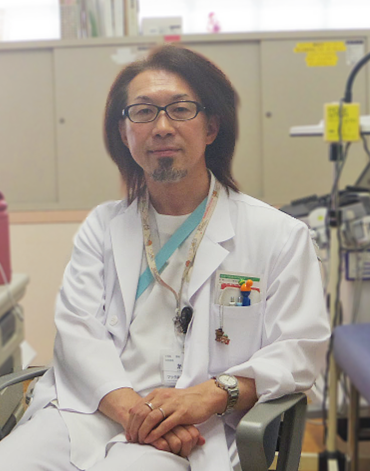
ページ内目次
食物アレルギーは子どもの病気?

食物アレルギーは患者の9割が10歳以下であり、およそ子どもの病気と言えますが、18歳以上の成人例も5%程度を占めており、また近年成人例の報告も増加傾向にあり、年齢を問わず今後も増加が予想されています。
診断へのアプローチ

食物アレルギーを疑うエピソード(食品摂取後に何らかの誘発症状が出現すること。特に、摂取により誘発症状が繰り返しみられること。)があれば、検査で確認し診断する流れが一般的です。
症状

誘発症状としては、
以上が単独、もしくは組み合わせて出現し、それら症状の程度や持続性によって重症度が評価されます。
特に2臓器以上に症状が出現・急速に進行し、命の危険を感じるほど重篤な状態をアナフィラキシーと呼びます。
食品に含まれる毒や成分により食物アレルギーに似た症状が出現することもありますが、誰でも症状がみられるものはアレルギーとは言わず、一部の人で過敏症状が出現するもののうち、食物蛋白などの食物抗原に対する免疫反応の結果として症状が出現するものを食物アレルギーと呼びます。
- 皮膚・粘膜症状(皮疹や痒みなど)
- 消化器症状(嘔吐・腹痛・下痢など)
- 呼吸器症状(咳・鼻汁・息苦しさなど)
- 循環器症状(顔色不良・頻脈あるいは徐脈など)
- 神経症状(意識混濁など)
以上が単独、もしくは組み合わせて出現し、それら症状の程度や持続性によって重症度が評価されます。
特に2臓器以上に症状が出現・急速に進行し、命の危険を感じるほど重篤な状態をアナフィラキシーと呼びます。
食品に含まれる毒や成分により食物アレルギーに似た症状が出現することもありますが、誰でも症状がみられるものはアレルギーとは言わず、一部の人で過敏症状が出現するもののうち、食物蛋白などの食物抗原に対する免疫反応の結果として症状が出現するものを食物アレルギーと呼びます。
検査
血液検査
診断のための検査としては、他のアレルギー疾患同様に血液検査がまず行われることが多いと思われます。一度に複数の食品に対し免疫反応が起こりうるかどうかを(採血の痛み以外は)体への負担なく調べることができて便利ですが、食品により結果の解釈に注意が必要であり、数値が高くても症状が出るとは限らず、逆に低いからと言って出ないとも限らず、評価には知識と経験が必要になります。
最近ではより診断精度を高めるため、食品に複数含まれている蛋白質のうち特にアレルギーに関与するもの(アレルゲンコンポーネント)だけを狙い撃ちして調べる検査も、いくつかの食品については保険適応で行えるようになっています。
最近ではより診断精度を高めるため、食品に複数含まれている蛋白質のうち特にアレルギーに関与するもの(アレルゲンコンポーネント)だけを狙い撃ちして調べる検査も、いくつかの食品については保険適応で行えるようになっています。

皮膚プリックテスト
皮膚プリックテストは精製された食品エキスや生の果汁などを皮膚に滴下した上から出血しない程度に針で刺して、刺したところが腫れたり赤くなったりする反応を見てアレルギーの有無を調べる検査になります。血液検査と異なり実際に体の反応を観察するという点でより高い診断精度を期待したいところですが、実際のところプリックテスト陽性でも食べて症状の出ない偽陽性例が割とあります。また、反応が刺した皮膚局所に留まらずアナフィラキシーに発展することも稀ながらあるため、必ずしも安全と言い切れない点にも注意が必要です。何度も針で刺す苦痛も小児には酷ですので当科では行っていません。
食物経口負荷試験
結局のところ診断のための最も確実な検査としては、実際に食品を食べて症状が出るのか出ないのかを確認する食物経口負荷試験に帰着します。とは言え、食物アレルギーが疑われる患者さんに何の準備もなくいきなり食品を摂取させれば、重大な事故に繋がる危険があります。予測される重症度の評価や摂取させる食品の量について事前に綿密な計画を立て、万が一の事態にも対応できる準備を整えた上で実施する必要があります。
食物経口負荷試験は診断だけではなく、どの程度食べればどの程度の症状が出るか、逆に言えばどれくらいの量までなら安全に食べられるかという一線を見極める点でも有用な検査です。と言うのも、現在の食物アレルギーの治療・管理の大前提は『食品の除去は必要最小限とし、安全な量を食べ続けて早期の耐性獲得を目指す』こととなっているからです。
食物経口負荷試験は診断だけではなく、どの程度食べればどの程度の症状が出るか、逆に言えばどれくらいの量までなら安全に食べられるかという一線を見極める点でも有用な検査です。と言うのも、現在の食物アレルギーの治療・管理の大前提は『食品の除去は必要最小限とし、安全な量を食べ続けて早期の耐性獲得を目指す』こととなっているからです。
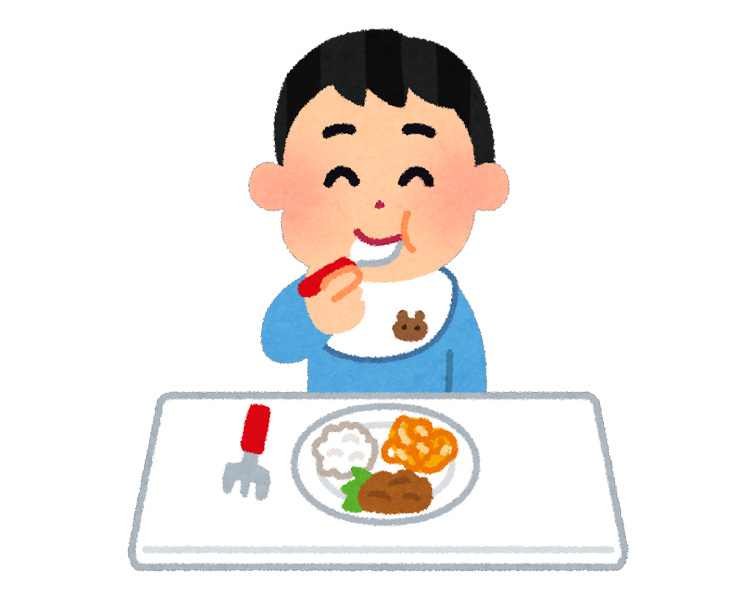
原因は?予防は可能?
20年遡れば、乳児の離乳食開始は遅い方が良く、特に卵などリスクの高い食品は1歳を過ぎてから開始するのが良い、という保健指導が世界中で赤ちゃんの保護者向けに行われていました。また血液検査で原因と疑われる食品が1つ見つかれば、芋づる式にあれもこれも食べてはダメといった指導がアレルギー専門医によって行われたために、栄養障害を起こす子どもが全国で多発していました。今では何れも誤った指導であったと認識されています。現在、国内外の公的機関が発行している離乳食の手引きでは、軒並み生後6カ月までには離乳食を開始するように指導されており、日本小児アレルギー学会食物アレルギー委員会からは『鶏卵アレルギー予防のために、特に鶏卵アレルギーのハイリスク乳児では湿疹の治療を充分に行った上で、生後6か月を目途に微量の加熱鶏卵摂取を開始する方が良い』との提言が出されています。すでに食物アレルギーを発症している乳児では対応が異なりますが、国内外の様々な食品に関する研究からは、基本的に早く食べ始めた方が食物アレルギーの予防に繋がるという流れが見受けられます。この点に関してはまだまだ食品によっては異論もあり、結論が出ていないものもありますので注意深く対応していく必要があります。
最近20年間で食物アレルギーに関する研究成果・発見が世界的に相次ぎ、爆発的に病気としての理解が進みました。食品摂取後速やかに誘発症状が出現する即時型症状、花粉症に関連して果物や豆乳の摂取で口や喉に限定した症状がみられる花粉-食物アレルギー症候群など複数のタイプに分類でき、対処法も異なること。食品を食べることが原因で過敏さを獲得するというよりも、湿疹(炎症を起こした皮膚)や気管支炎・腸炎(炎症を起こした粘膜)の患部から食物抗原が体内に侵入し、免疫反応が起こり全身の過敏さが成立した状態で食べることにより、全身様々な臓器で誘発症状がみられる様になることなどが分かってきました。社会的にも食物アレルギーの認知が進み、主婦や調理師が水仕事の手荒れから食物アレルギーを発症した例、髭剃り後ローションや石鹼・口紅など化粧品・日用品に含まれる食物抗原により発症した例など成人での発症報告も増えています。林業関係者と獣肉アレルギー、サーファーと納豆アレルギーなど環境・職業的にみられやすいものもあります。
最近20年間で食物アレルギーに関する研究成果・発見が世界的に相次ぎ、爆発的に病気としての理解が進みました。食品摂取後速やかに誘発症状が出現する即時型症状、花粉症に関連して果物や豆乳の摂取で口や喉に限定した症状がみられる花粉-食物アレルギー症候群など複数のタイプに分類でき、対処法も異なること。食品を食べることが原因で過敏さを獲得するというよりも、湿疹(炎症を起こした皮膚)や気管支炎・腸炎(炎症を起こした粘膜)の患部から食物抗原が体内に侵入し、免疫反応が起こり全身の過敏さが成立した状態で食べることにより、全身様々な臓器で誘発症状がみられる様になることなどが分かってきました。社会的にも食物アレルギーの認知が進み、主婦や調理師が水仕事の手荒れから食物アレルギーを発症した例、髭剃り後ローションや石鹼・口紅など化粧品・日用品に含まれる食物抗原により発症した例など成人での発症報告も増えています。林業関係者と獣肉アレルギー、サーファーと納豆アレルギーなど環境・職業的にみられやすいものもあります。
おわりに
離乳食の進め方や保育園・学校における社会対応・患者指導など、食物アレルギーを取り巻く環境およびこれまで言われてきた常識は、この20年間で劇的に変化しました。患者さんの生活の質向上を第一に考え、新しい知見が得られれば、改めるべき点は改めていく姿勢が重要と考えます。

